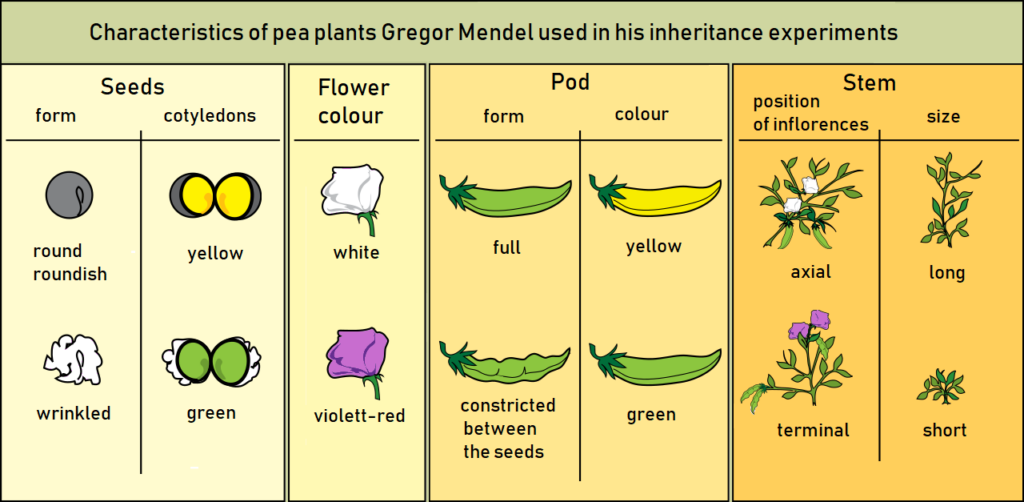人の知能(IQ)に大きな影響を与えているのは遺伝的な要因かそれとも環境要因かという問題は、長年にわたって大きな論争になってきました。
①20世紀はじめ頃まで:遺伝の影響を重視(生得説が優位)
②1920年代~1970年代:環境の影響を重視(環境説が優位)
③1970年頃~:遺伝と環境の相互作用論
④1980年代~現在:遺伝の影響の再認識(新・遺伝主義=生得説が優位)
⑤2000年頃以降:エピジェネティクス現象の発見(新・相互作用論:両方の重要性を再認識)
(出典:若林明雄 教養としての心理学講座 022年12月25日 有斐閣 126ページ)
以下、遺伝説や環境説を唱える主要な書籍、画期的な論文などをまとめておきます。
1883 Sir Francis Galton Inquiries Into Human Faculty and Its Development (Internet Archive全文) 24ページ(電子書籍43ページ)に優生学(eugenics)という言葉の導入がある。
1969 Arthur R. Jensen How much can we boost IQ and scholastic achievement? (IQと学業成績をどれほど増進できるか) Harvard Educational Reviews 39:1-123. (1969). (A.R.ジェンセン IQの遺伝と教育 岩井 勇児 (監訳) 昭和53年10月5日 黎明書房 に所収)IQが遺伝で決まるという非常にセンセーショナルな主張として捉えられ、人種差別などの問題と結びつけられて、大激震を引き起こした論文。カリフォルニア大学バークレー校教授ジェンセンを解雇すべきという学生運動が巻き起こるなどの騒動も。
IQと競争社会 (1975年) R.J.ヘアンスタイン、 岩井 勇児 | 1975/1/1 環境条件の不平等が克服され、機会均等が達成されればされるほど、遺伝的条件(IQ)によって社会階層への所属が決まるーーー全米に論争を巻き起こした問題の書。著者はハーバード大学教授。(黎明書房 書籍紹介文)
I.Q.の科学と政治 (1977年) - – 古書, 1977/2/1 L.J.カミン (著), 岩井 勇児 (翻訳) ジェンセンや、へアンスタイン、C.バート、シールズなどに代表される遺伝論者の見解と対立ーーーIQの遺伝論はイデオロギーの産物でしかないということを豊富な資料を駆使して論証したIQ環境論。(黎明書房 書籍紹介文)
1988. Genetic influence on general mental ability increases between infancy and middle childhood D. W. Fulker, J. C. DeFries and R. Plomin Nature Vol. 336 Issue 6201 Pages 767-9
2010/3/12 頭のでき―決めるのは遺伝か、環境か リチャード E ニスベット (著), 水谷 淳 (翻訳) 知能に影響する因子に関して、遺伝主義が主流な中で、環境主義を強く主張する内容のようです。
2012/7/1 遺伝子の不都合な真実―すべての能力は遺伝である (ちくま新書) 安藤 寿康
2015. Polderman, T., Benyamin, B., de Leeuw, C. et al. Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies. Nat Genet 47, 702–709 (2015). https://doi.org/10.1038/ng.3285 ”Despite a century of research on complex traits in humans, the relative importance and specific nature of the influences of genes and environment on human traits remain controversial.” (Abstract 冒頭)
2018. Savage, J.E., Jansen, P.R., Stringer, S. et al. Genome-wide association meta-analysis in 269,867 individuals identifies new genetic and functional links to intelligence. Nat Genet 50, 912–919 (2018). https://doi.org/10.1038/s41588-018-0152-6 “Intelligence is highly heritable” (Abstract 冒頭)
2021/9/21 Kathryn Paige Harden The Genetic Lottery: Why DNA Matters for Social Equality 邦訳:キャスリン・ペイジ・ハーデン遺伝と平等:人生の成り行きは変えられる 2023/10/18 双子研究やGenome-wide association study (GWAS)などの研究から遺伝的な要因が知能をある程度決めているということを説明しています。かなり注意深い言葉遣いで、人種差別などに利用されないような物言いをしているようです。「人生の成り行きは変えられる 」という邦題は内容とは合っていなくて、本書では遺伝が知能をある程度決めるということを受け入れたときの社会的な平等とは何かを議論している本です。人生を変えたいと願う個人が何をすればいいかを書いた本ではありません。
Doust, C., Fontanillas, P., Eising, E. et al. Discovery of 42 genome-wide significant loci associated with dyslexia. Nat Genet 54, 1621–1629 (2022). https://doi.org/10.1038/s41588-022-01192-y
2022. Okbay, A., Wu, Y., Wang, N. et al. Polygenic prediction of educational attainment within and between families from genome-wide association analyses in 3 million individuals. Nat Genet 54, 437–449 (2022). https://doi.org/10.1038/s41588-022-01016-z
2022. Abdellaoui, A., Dolan, C.V., Verweij, K.J.H. et al. Gene–environment correlations across geographic regions affect genome-wide association studies. Nat Genet 54, 1345–1354 (2022). https://doi.org/10.1038/s41588-022-01158-0 educational attainment polygenic scores capture gene–environment correlations