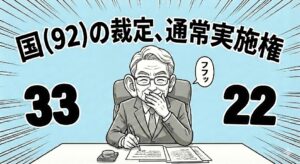語呂合わせ暗記法:国(92)の裁定、通常実施権、耳、フフッ。
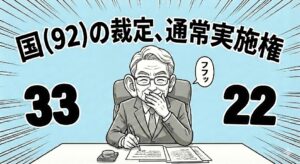
特92裁定通常実施権 意33 実22
語呂合わせの法の順番は、特許→意匠→商標→実用新案 にしています。商標は今の場合該当するものがないので、特許→意匠→実用新案 の順に、92 33 22 です。
TAC枝別問題集(弁理士過去問)をやっていて理解できなかった2つの問題、令2特19(ホ)と平20特42(ニ))の解説をAI3者にお願いしてみました。
令和2年度 弁理士試験 短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集 【特許・実用新案】19 特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。
(ロ) 専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
(ハ) 通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
(ニ) 通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。
(ホ) 特許権者甲が、特許法第 92 条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。
弁理士試験 平成20年42(ニ) https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-mondai/document/h20tanto/question.pdf
〔42〕特許に関する権利の移転等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも、分割又は変更に係るものでもないものとする。
(イ) 特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず、特許庁長官に届け出なければならない。
(ロ) 職務発明について特許を受ける権利の承継に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。
(ハ) 特許を受ける権利を有する甲及び乙は共同して特許出願Aをした。その後、 丙は甲の特許を受ける権利の持分の譲渡を受けた旨の譲渡証書を偽造して出願人を甲から丙に変更する出願人名義変更の届出を特許庁長官に行い、 Aについて 乙及び丙を特許権者とする特許権の設定の登録がなされた。この場合において、 丙の名義になっている当該特許権の持分につき、 甲による、丙 から甲への移転登録請求が認められることがある。
(ニ) 特許権者甲は、特許権者乙の有する先願に係る特許権について、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権の設定の裁定を請求をした。これに対し、 乙は甲の有する特許権について、同条第4項の規定による通常実施権の設定の裁定を請求した。その後、甲及び乙 は各自の請求に係る通常実施権の設定を得た。この場合、乙の当該通常実施権は、 乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。
(ホ) 特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。
令和2年19(ホ)と平成20年42(ニ)の違いの生成AI3者による解説
Geminiは間違った回答を最初くれましたし、Claudeもやはり問題文を正しく読み取りませんでした。ChatGPTが一番、信頼できそうな結果となりました。
ChatGPT 5.2:
この 令和2年19(ホ) と 平成20年42(ニ) は、ほぼ同じ92条裁定の話をしているように見えて、結論が逆になる典型的な“ひっかけ対比”です。ポイントは 「どの通常実施権か」 と 「どの権利が移転するのか」 です。以下、1問ずつ丁寧に分解して説明します。
① 令和2年19(ホ)の構造と結論
問題文(要約)
- 甲:特許権Aの特許権者
- 乙:特許権Bの特許権者
- 両者は 特許法92条(利用関係)にある
- 甲は
👉 「Aを実施するために必要だから」
👉 Bについて通常実施権の裁定を受けた
- 甲はその通常実施権を使って
👉 A発明の実施事業を行っている
- その後
👉 特許権Aが、その事業と分離して丙に移転
- 問題:
Bについての甲の通常実施権も、丙に移転するか?
結論
❌ 移転しない(誤り)
理由(ここが核心)
92条裁定による通常実施権は、
「自己の特許発明を実施するために必要な限度で」
与えられる人格的・目的限定的な権利
です。つまりこの通常実施権は:
にだけ認められたもの。
👉 Aそのものが第三者(丙)に移転してしまったら、「甲がAを実施するため」という前提が消滅する
したがって、
- 事業と分離してAが移転
- ⇒ 92条裁定の前提消滅
- ⇒ Bについての通常実施権は丙に承継されない
② 平成20年42(ニ)の構造と結論
問題文(要約)
- 甲・乙はそれぞれ特許権者
- 甲は
👉 乙の先願特許について92条3項の裁定請求
- 乙も
👉 甲の特許について92条4項の裁定請求
- 双方が相互に通常実施権を取得
- その後、
👉 乙の特許権が実施の事業と分離して移転
- 問題:
乙の特許権についての通常実施権は消滅するか?
結論
❌ 消滅しない(誤り)
理由(令和2年との決定的違い)
ここでの通常実施権は、
- 甲が
- 乙の特許を
- 甲自身の特許発明を実施するために
取得したもの。
そして重要なのは:
👉 通常実施権を設定した側(乙)の特許権が移転しても、
通常実施権は原則として存続する
という特許法の大原則。
- 通常実施権は 特許権に対抗力を持つ独立の利用権
- 特許権者が変わっても消えない(登録が要件になる場合は別)
したがって、
- 乙の特許権が第三者に移転しても
- 甲の通常実施権は そのまま存続
③ 両者の「本質的な違い」を一言で
| 観点 |
令和2年19(ホ) |
平成20年42(ニ) |
| 問題の焦点 |
通常実施権が承継されるか |
通常実施権が消滅するか |
| 通常実施権の性質 |
自己特許実施のための目的限定権 |
独立した利用権 |
| 何が移転? |
通常実施権者自身の特許権 |
通常実施権設定者の特許権 |
| 結論 |
❌ 承継されない |
❌ 消滅しない |
④ 試験的な覚え方(超重要)
✅ 92条裁定の鉄則
「誰のための、何のための通常実施権か」を必ず確認せよ
- 自己特許を実施するための裁定実施権
→ その自己特許を失えば ついてこない
- 他人の特許に設定された通常実施権
→ 特許権が移転しても 原則消えない
プロンプト:
「乙の特許権が移転」は、「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」の話?それとも、「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話?
Chat GPT5.2:
ここは文言解釈で一度つまずくと抜けられないポイントなので、
結論→理由→見分け方、の順で整理します。
結論(先に)
**「乙の特許権が移転」**とは、
✅ 乙が“特許権者である側”として保有していた自己の特許権が移転する場合
を指します。
❌ 「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転する」という意味ではありません。
なぜそう読まなければならないのか
問題文(平成20年42(ニ))を、主語と対象を明確にして分解します。
① 問題文の前提整理
② 裁定の対応関係
| 誰が |
どの特許について |
何を得たか |
| 甲 |
乙の特許権 |
通常実施権(92条3項) |
| 乙 |
甲の特許権 |
通常実施権(92条4項) |
問題の核心文
「この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。」
ここで出てくる 2つの「乙」 を区別するのが重要です。
文法的な対応関係
「乙の当該通常実施権」
→ 乙が裁定で取得した
→ 甲の特許権についての通常実施権
「乙の当該特許権」
→ 乙が特許権者として保有している特許権
→ 乙自身の特許権
つまり問題文はこういう意味
乙が
・甲の特許権について裁定通常実施権を取得したが、
・その後、乙自身の特許権が
実施事業と分離して第三者に移転した場合、
👉 その裁定通常実施権は消滅するか?
という問いです。
なぜ「甲が通常実施権を持っている対象の特許権」ではないのか
理由①:文言がそう書いていない
もしその意味なら、問題文は
「甲の特許権が移転したときは」
と書かれるはずです。
「乙の特許権が移転」と明示している以上、
それは 乙が権利者である特許権 しか指しません。
理由②:92条裁定のロジックに合わない
92条の裁定通常実施権は、
- 自己の特許発明を実施するため
- 他人の特許を利用する権利
です。
したがって、
- 乙が
- 甲の特許について持っている通常実施権が
- 乙自身の特許権の移転によって消えるか
という構成でないと、「自己特許を失ったらどうなるか」という法的意味が出てきません。
試験的な一行整理(これが使える)
「Aの当該特許権が移転」
= Aが“特許権者として保有していた特許権”の移転
「Aの当該通常実施権」
= Aが裁定等で“取得した利用権”
最後に超重要な対比(令和2年19(ホ)との関係)
| 問題 |
何が移転する? |
結論 |
| 令和2年19(ホ) |
通常実施権者自身の特許権 |
通常実施権は承継されない |
| 平成20年42(ニ) |
通常実施権者自身の特許権 |
通常実施権は消滅しない |
👉 同じ「自己特許の移転」でも、
「承継の可否」と「消滅の有無」を聞いている点が違う
というのが、出題者の一番いやらしいポイントです。
プロンプト:
承継されないけど、消滅もしていないということね。つまりこの2問は全く同じ問題で、聞くポイントをちょっと変えただけ?
ChatGPT 5.2:
はい、結論の理解はほぼ正解です。ただし、「全く同じ問題」ではありません。
同じ92条裁定という素材を使いながら、短答的に“別の法的性質”を聞いている、という位置づけが一番正確です。
結論を一行で整理
令和2年19(ホ)と平成20年42(ニ)は、
事実関係の骨格は同じだが、
聞いている法的ポイント(評価軸)が異なる。
まず、あなたの理解の確認
「承継されないけど、消滅もしていない」
これは 平成20年42(ニ) について、正しい整理です。
- 通常実施権は
👉 第三者(丙)に承継されない
- しかし
👉 乙の手元では消滅しない
では、何が違うのか(ここが本質)
共通点(素材レベル)
両方とも:
- 特許法92条の裁定通常実施権
- 「自己の特許発明を実施するため」という目的限定
- その後に 特許権が事業と分離して移転
違い①:聞いている「法的評価」
| 問題 |
問われていること |
| 令和2年19(ホ) |
第三者に承継されるか? |
| 平成20年42(ニ) |
本人の権利として消滅するか? |
👉 承継 ≠ 消滅
この切り分け自体を理解しているかを試している。
違い②:問題文が想定する「視点」
令和2年19(ホ)
- 視点:丙(第三者)
- 問題意識:
「この通常実施権、Aと一緒についてくるの?」
→ NO(ついてこない)
平成20年42(ニ)
- 視点:乙(元の実施権者)
- 問題意識:
「自己特許を失ったら、
その裁定通常実施権って消えるの?」
→ NO(消えない)
ここが“同じに見えて同じでない”理由
92条裁定通常実施権は:
- 物権的でも
- 完全に債権的でもない
- 目的拘束付きの法定利用権
という 中途半端でクセの強い性質を持っています。
だから:
この 両立しにくい二つを、
別々の問題で確認しているのがこの2問。
試験委員の本音(推測だけど、ほぼこれ)
「92条の通常実施権を“承継できない=消える”と短絡的に理解している受験生を落としたい」
超短答用・最終まとめ(これを覚えておけばOK)
92条裁定通常実施権は:
- ✅ 第三者には承継されない
- ❌ だからといって直ちに消滅するわけではない
- ❌ 特許権の移転だけで当然消滅しない
あなたの一言評価
「聞くポイントをちょっと変えただけ?」
👉 素材は同じ、聞き方は意地悪に変えている
👉 だから“似ているけど別問題”
短答としては、
「同じと思った瞬間に落とし穴」
という、かなり良問(悪問)です。
ChatGPTによる説明で、言い尽くされたと思いますが、一応ClaudeとGeminiの回答も載せておきます。
Claude Opus 4.5:
これは良い質問ですね。両方とも特許法92条の裁定通常実施権に関する問題ですが、状況が微妙に異なります。整理して説明します。
前提:特許法92条の構造
92条3項:後願特許権者(甲)が、先願特許権者(乙)の特許権について通常実施権の裁定を請求できる
92条4項:上記の裁定を受けた場合、先願特許権者(乙)も、後願特許権者(甲)の特許権について通常実施権の裁定を請求できる(クロスライセンスの強制)
令和2年19(ホ)の状況
甲が92条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするため、乙の特許権Bの通常実施権を得た。 甲の特許権Aが事業と分離して丙に移転する場合、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転するか?
答え:移転しない(×)
理由
94条2項により、92条の裁定による通常実施権は:
- 実施の事業とともに移転する場合
- 特許権等の移転に伴って移転する場合
- 相続その他の一般承継の場合
にのみ移転します。
この問題では「事業と分離して」特許権Aが移転するので、通常実施権は移転しません。甲の通常実施権は甲に残り(ただし実施の基礎を失うので実質的に意味がなくなる)、丙には移転しません。
平成20年42(ニ)の状況
甲(後願)が乙(先願)の特許権について92条3項の裁定で通常実施権を得た。 乙も甲の特許権について92条4項の裁定で通常実施権を得た。 乙の特許権が事業と分離して移転したとき、甲の通常実施権は消滅するか?
答え:消滅しない(×)
理由
ここで問われているのは「乙の特許権(=甲が通常実施権を持っている対象の特許権)が移転した場合」です。
通常実施権は当然対抗制度(99条)により、特許権が移転しても通常実施権者は新特許権者に対抗できます。つまり、乙の特許権が丙に移転しても、甲は引き続きその特許発明を実施できます。
甲の通常実施権が消滅するのは、甲自身の特許権が事業と分離して移転した場合です(94条2項の反対解釈)。
両者の違いのポイント
| 項目 |
令和2年19(ホ) |
平成20年42(ニ) |
| 移転するのは |
甲の特許権A(通常実施権の基礎) |
乙の特許権(通常実施権の対象) |
| 問われている効果 |
甲の通常実施権が丙に移転するか |
甲の通常実施権が消滅するか |
| 答え |
移転しない |
消滅しない |
| 根拠 |
94条2項(事業と分離なので移転不可) |
99条(当然対抗制度により存続) |
要するに:
- 自分の特許権(裁定の基礎)が事業と分離して移転 → 通常実施権は移転しない(94条2項)
- 相手の特許権(通常実施権の対象)が移転 → 通常実施権は消滅しない(99条で対抗)
この違いを問うているわけです。
プロンプト:乙の当該通常実施権 って、どっちのことを指すの?甲からもらった裁定通常実施権のこと?それとも、乙自身がもともと持っていた方?
Claude Opus 4.5
するどい質問ですね。問題文をもう一度読み直してみましょう。
(ニ) …この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。
「乙の当該通常実施権」は、乙が92条4項で甲の特許権について得た通常実施権のことです。
状況を整理すると
- 甲:後願特許権者 → 92条3項で乙の特許権について通常実施権を得た
- 乙:先願特許権者 → 92条4項で甲の特許権について通常実施権を得た
問題文は「乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が…移転したときは、消滅する」と言っています。
この問題の構造
乙が持っている通常実施権(甲の特許権に対するもの)は、乙自身の特許権の実施のために得たものです。
94条2項によれば、92条の裁定通常実施権は「特許権の移転に伴って移転する」場合に移転できます。
ここで乙の特許権が事業と分離して第三者に移転した場合:
- 乙は自己の特許権を失う
- しかし乙が甲の特許権について持っていた通常実施権は乙に残る(移転しない)
- でも乙にとってはもはや意味がない(自己の特許発明を実施する基礎がないから)
しかし「消滅する」わけではありません。 移転しないだけで、形式的には乙に残ります。
答え
(ニ)は**誤り(×)**です。
乙の特許権が事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は「消滅」はしません。移転しないだけで乙に残ります(実質的には無意味になりますが)。
私の前回の説明の訂正
前回、「乙の特許権が移転」を「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」と読んでしまいましたが、正確には上記のとおり「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話でした。結論(×)は同じですが、理由が違いますね。失礼しました。
:
Gemini 3
(Geminiだけ間違えた回答をしてきたので、答えを教えて解説をやり直してもらった)
大変失礼いたしました!ご指摘の通りです。「92条」という一括りで考えてしまいましたが、平成20年の問題は**「対抗裁定(92条4項)」の枝であり、適用される条文が特許法第94条第5項**になるため、結論が変わります。混乱させてしまい申し訳ありません。改めて、**「なぜ一方は消滅し、もう一方は消滅しないのか」**を整理して解説します。
1. 2つの通常実施権の「移転ルール」の違い
この問題の鍵は、**「92条3項(通常の裁定)」と「92条4項(対抗裁定)」**で、移転・消滅のルールが別々に規定されている点にあります。
① 令和2年 19(ホ) : 92条3項(通常の裁定)
-
根拠条文: 第94条2項
-
ルール: 「特許権」+「実施の事業」とセットでなければ移転できない。
-
分離した場合: 事業と分離して特許権だけ移転すると、通常実施権は消滅する。
-
問題の結論: 「丙に移転する」とあるので、誤り(×)。
② 平成20年 42(ニ) : 92条4項(対抗裁定)
-
根拠条文: 第94条5項
-
ルール: その通常実施権者の「特許権」とセットで移転する。
-
ポイント: 条文(94条5項)には、2項のような**「実施の事業とともにしなければならない」という要件も、「事業と分離したら消滅する」という規定もありません。**
-
分離した場合: 事業と分離して特許権が移転しても、通常実施権は特許権にくっついて移転し、消滅しません。
-
問題の結論: 「消滅する」とあるので、誤り(×)。
2. なぜ「対抗裁定(92条4項)」は事業と分離しても消滅しないのか?
ここが一番の「なぜ?」ですよね。制度の趣旨から考えると納得しやすくなります。
- 通常の裁定(92条3項):「自分の特許(A)を実施したいから、邪魔な他人の特許(B)を使わせてくれ!」という「お願い」から始まる権利です。**「事業を救う」**ことが目的なので、事業と切り離されたら存在理由がなくなり、消滅します。
- 対抗裁定(92条4項):「特許Bを使わせろと言われたから、代わりにこっちもあんたの特許Aを使わせろ!」という、いわば**「お返し(クロスの関係)」で発生した権利です。この権利は、相手に自分の特許を使わせるという「負担」に対する「見返り」としての性格が強いため、事業との密接度よりも、「自分の特許権とセットであること」**が重視されます。そのため、事業と離れても特許権が移転する限り、消滅せずに守られるのです。
3. まとめ表
今回の2つの問題を比較すると、以下のようになります。
| 項目 |
令和2年 19(ホ) |
平成20年 42(ニ) |
| 裁定の種類 |
92条3項(自ら請求) |
92条4項(対抗して請求) |
| 適用条文 |
94条2項 |
94条5項 |
| 事業との分離 |
消滅する |
消滅しない |
| 問題文の記述 |
「移転する」 |
「消滅する」 |
| 解答(正誤) |
誤り(×) |
誤り(×) |
[!IMPORTANT]
試験対策のポイント
「裁定通常実施権の移転」が出てきたら、まず**「92条4項(対抗裁定)かどうか」**をチェックしてください。
私の確認不足で最初にお騒がせしてしまいましたが、この「94条2項 vs 5項」のひっかけは非常に受験生が間違いやすいポイントです。今のうちにこの違いをクリアにできたのは、大きなアドバンテージになるはずです!
プロンプト:
「乙の特許権が移転」は、「甲が通常実施権を持っている対象の特許権が移転」の話?それとも、「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権が移転」という話?
Gemini 3:
非常に鋭い視点です!ここが特許法第94条の最もややこしい「主語」の問題ですね。結論から言うと、後者の「乙が自己の実施のために必要だった乙自身の特許権(特許権B)」が移転した話をしています。混乱を解くために、「誰の特許権」に「誰の実施権」がくっついているのか、整理して解説します。
1. 権利の「親子関係」で理解する
平成20年の問題(対抗裁定)のケースでは、乙は以下の状態にあります。
この通常実施権(子)は、単独で存在しているのではなく、乙の特許権B(親)に**「おまけ」**としてくっついているイメージです。
「乙の特許権が移転」とはどういう意味か?
問題文で「乙の当該特許権が……移転した」と言っているのは、**「親である特許権Bを、乙が誰か(第三者)に売った」**という状況を指しています。
このとき、おまけである「甲の特許権Aを使える権利(子)」がどうなるかというと……
2. なぜ「甲の特許権」の移転ではないのか?
もし「甲の特許権A(使わせてもらう対象)」が移転した場合は、第99条(通常実施権の対抗力)の問題になります。
今回の問題(94条)はあくまで、**「実施権を持っている人(乙)が、自分の持ち物(特許権B)を処分したときに、実施権も一緒に連れていけるか?」**を問うています。
3. 令和2年と平成20年の「主語」を並べて比較
混乱の正体は、この2問で「主語(実施権を持っている人)」の立ち位置が違うことです。
| 問題 |
実施権を持っている人 |
その人が元々持っている特許権(親) |
移転した「当該特許権」とは |
| 令2-19(ホ) |
甲(最初に裁定を請求した人) |
特許権A |
甲の特許権A |
| 平20-42(ニ) |
乙(対抗して裁定を受けた人) |
特許権B |
乙の特許権B |
どちらも「自分の特許権」を売った時の話
どちらの問題も、**「実施権をもらった側の人が、自分の特許権(事業のベースになる権利)を手放したときに、おまけの実施権はどうなるか?」**という同じ構図を、違う立場の人物(甲か乙か)で聞いているだけです。
まとめ
「乙の当該特許権」= **「乙がもともと持っていた、裁定のベースになった特許権B」**のことです。
対抗裁定でもらった権利は、自分の特許権との結びつきが非常に強いため、事業と切り離されても「特許権」さえ移転すれば生き残る(消滅しない)、という非常に珍しい特例ルール(94条5項)が適用されているわけです。